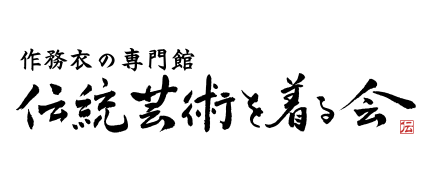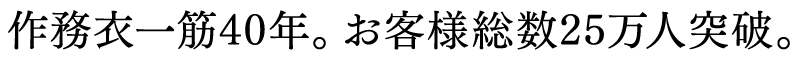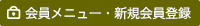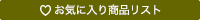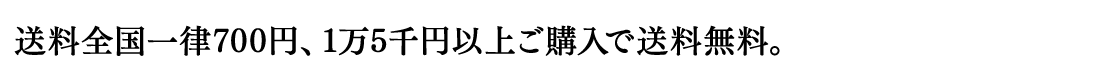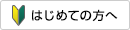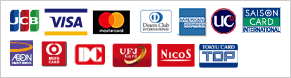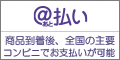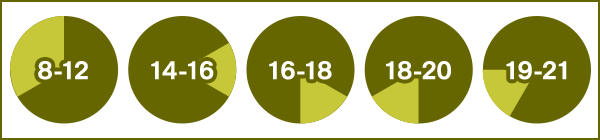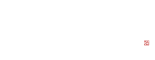布を刺す。刺子の物語

雪深い北国に咲いた白い花、素朴にして端正な“刺子模様”

炉端に座った母と娘が黙々と針を使っています。鉄びんがチンチンと鳴り湯気がゆらゆらと立ちのぼっています。雪はしんしん、外は一面の銀世界。時間が静かに流れてゆき、母親の手元では、藍地に白い花が咲こうとしています…。
こんな光景が時を越えて目に浮かんできます。今回は、雪深い北国から生まれた、質素で素朴でありながら端正な輝きを見る人に与えてくれる“刺子(さしこ)”という技法についてお話しましょう。
刺子とは、簡単に言えば布地に補強、保温、装飾を加えるために刺し縫いをすることです。
衣服に刺しを施す手法は全国各地で見られるもので、その発祥は定かではありません。
しかし、最も古いとされ有名なのは、藍染の麻地に巧みな刺し模様を配し、他の地方では見られない独自の服飾美を築き上げた<津軽こぎん>が上げられます。
衣服の補強と保温。刺子のはじまりは、なぜか悲しい…。

その昔、木綿は大変貴重な素材でした。特に綿の栽培が出来なかった東北の地においては、百姓農民が木綿を衣服として着用することは藩令によって禁止され、もっぱら麻地を着用していたとされています。
夏はともかく、寒さ厳しい北国の冬を麻の着物で越すのはちょっと無理。そこで衣服の補強と保温を図るために、麻の白糸で布目を一面に刺して塞いだのが刺子のはじまりだったのです。
それがいつの頃だったか、これも定かではありませんが、津軽藩江戸定府の士、比良野貞彦が天明八年に著した「奥民図集」に、
『布を糸にてさまざまの模様を刺すなり。甚見事なり。男女共に着す。多くは紺地に白き糸を以って刺す』
と記してあることから、この時代にはすでに刺子の手法は確立していたと思われます。
農家の娘は、五歳になると針を持たされ、母親と共に毎日のように刺し続けます。やがて嫁に行き、生まれた娘へ…とこの手法は代々継承されていったのです。
身近な自然風土をテーマにした模様は、鮮烈で感動的――

囲炉裏を囲んで黙々と刺し続けるこの“仕事”の中で、娘たちはただ単に実用という目的以外に、飾る歓びを見つけ出します。それが、実に見事な刺子模様を生み出していったのです。
現存する模様を見て見ますと、その発想は身近な自然の風土から生まれているのがよく分かります。猫の目・豆っこ・花・竹・石だたみ…などと独創性豊かに刺されていて、その素朴さとエスプリには感動を覚えるほど。
藍地に白のコントラストは実に端正で、怠惰な飾り立てに飽きた現代人の感覚に鮮烈に訴えるものがあります。
色刺しや伊達刺しも現れ、その服飾美に大きな注目が。

明治に入ると木綿の着用が認められ、刺し糸が白い綿糸に変り、模様がさらに鮮やかに映えるようになります。
この頃から、刺子は実用性より服飾美が注目されるようになったのです。そして鉄道の普及が、刺子の役割に終わりを告げました。
しかし、この北国に芽生えた刺子の素朴さや美しさや滅びることなく現代まで伝えられてきました。
それは単なる模様ではなく、それに込められた“生きる歓び”や刺し続ける乙女たちの心の輝きが万人の胸を打つからに他ならないからでしょう。
この刺し手法は北国以外でも古くから見られます。例えば、江戸中期に「鳶、人足、火消しは必ず刺す」と決めがあったとか。火消し装束などは、いわゆる半纏刺しとしてあまりにも有名。色刺しや伊達刺しの傾向もすでに現れています。
合理的な刺子織の開発と進歩で、その情緒を楽しむ。

衣服の材料が溢れんばかりに豊富な現代。皮肉にも、切ない想いから生まれた刺子模様が大変に注目を集めています。実用性を重視した武道着はともかく、ファッションとして幅広く取り入れられているようです。
合理性の面から、一針ずつの刺し手法ではなく、いわゆる刺子織りの技術も開発されました。その良否はともかく、現在では手軽にこの刺子の風情が楽しめるようになったのです。
貧しさを見事な知恵で着る歓びに変えた先人たちの心を、受け止めてみたいものです。